Q1.免疫の役割は?
Q2.免疫が不利に働く例を挙げよ
Q3.免疫はどのような機能と考えられているか
Q4.免疫のシステムはどのように作用するか
Q5.一次リンパ器官には何があるか
Q6.一次リンパ器官は何に関わるか
Q7.二次リンパ器官にはどのようなものがあるか
Q8.二次リンパ器官はどのような場となるか
Q9.免疫担当細胞は何からできるか
Q10.骨髄系幹細胞から何が分化・成熟してできるか
Q11.リンパ系幹細胞からはリンパ球ができ、分化の違いによってT細胞とB細胞になるが、T細胞はどのように分化したものか
Q12.T細胞のTは何からきているか
Q13.B細胞はどこで分化・成熟するか
Q14.B細胞は分化・成熟したあと、どうなるか
Q15.B細胞のBは何からきているか
Q16.自然免疫の特徴を挙げよ
Q17.獲得免疫の特徴を挙げよ
Q18.自然免疫の一種に皮膚のはたらきがあるが、皮膚による強固な物理的バリアーについて3点
Q19.自然免疫の一種に粘膜のはたらきがあるが、粘膜による異物の侵入を防ぐバリアーについて
Q20.粘液・分泌液の作用について
Q21.咳やくしゃみという防御反応について
Q22.呼吸器における異物の侵入を防ぐバリアーについて
Q23.消化管における異物の侵入を防ぐバリアーについて
Q24.腸管の蠕動運動・分節運動による異物の侵入を防ぐバリアーについて
Q25.腸液の分泌増加による異物の侵入を防ぐバリアーについて
Q26.泌尿器の異物の侵入を防ぐバリアーに対する機能
について
・病原体の侵入・増殖に対する整体防御機構の役割
・腫瘍に対する排除
・腫瘍に対する排除
・移植の際の反応
・アレルギー
・自己免疫疾患
など
・アレルギー
・自己免疫疾患
など
免疫は、単なる感染防御機構ではなく、より広く「自己」には作用せずに「非自己」にのみ作用する生物の持つ本質的な機能と考えられている。
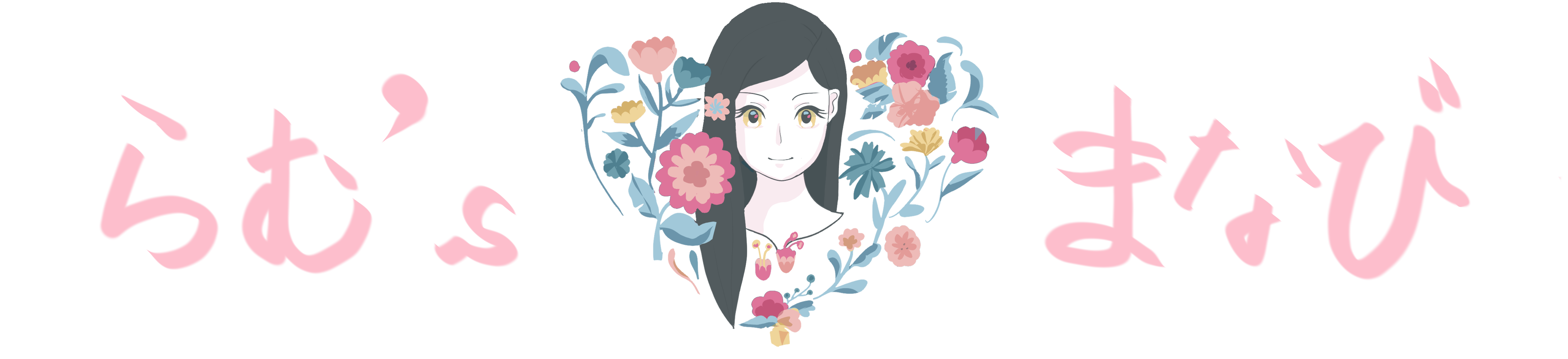


コメント