Q1.補体は主にどこから産生されるものか
Q2.補体の成分はいくつあるか
Q3.補体成分で最も多いのは何か
Q4.補体の活性化は3種類の異なるきっかけで起こるが名称を挙げよ
Q5.古典経路は何が存在する場合の活性経路か
Q6.古典経路はどのように活性化が始まるか
Q7.古典経路ではどの順に補体活性化が進むか
Q8.副経路の特徴を述べよ
Q9.レクチン経路の特徴を述べよ
Q10.ちなみに、最初に発見された活性経路は何か
Q11.C3の活性化以降の経路は3つの経路とも共通か
Q12.C3はC3αとC3bに開裂するが、C5以下を活性化してさらに反応を進ませるのはC3αとC3bのどちらか
Q13.C3αとC5αの役割は何か
Q14.C5αは走化性因子であるが、具体的にどのような機能があるか
Q15.C5bは走化性因子であるが、具体的にどのような機能があるか
Q16.アナフィラトキシンに関係する補体は何か
Q17.膜傷害性複合体の形成に関係する補体は何か
Q18.オプソニン効果(作用)とはどんな作用か
主に肝臓で産生されるタンパク質群のこと。
C1(補体第1成分)からC9までの9つ。
C3(補体第3成分)
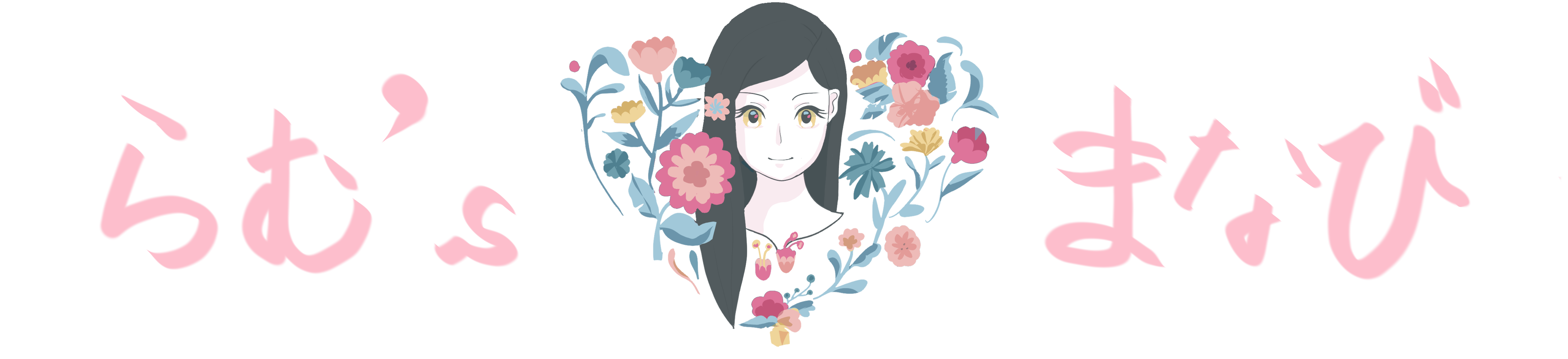


コメント