Q1.薬剤耐性菌とは何か
Q2.通常の有効薬剤濃度では発育が阻止される菌をなんと呼ぶか
Q3.化学療法とは何か
Q4.βラクタマーゼとは何か
Q5.抗菌薬に対する薬剤耐性菌の耐性機構には何があるか
Q6.薬剤透過性の低下による薬剤耐性について
Q7.薬剤作用点(菌の構造)の変化による薬剤耐性について
Q8.交差耐性とは何か
Q9.交差耐性はどんな薬剤にみられるか
Q10.菌が薬剤耐性を持つ方法2つは何か
Q11.薬剤耐性菌への突然変異は染色体の変異によるものだが、他の菌へ伝達されるか
12.薬剤耐性遺伝子の水平伝播による耐性獲得ついて
Q13.主な薬剤耐性菌を列挙せよ
Q14.メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)について
Q15.バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)について
Q16.ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)について
Q17.βラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性インフルエンザ菌(BLNAR)について
Q18.基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)産生菌について
Q19.カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)について
Q20.多剤耐性緑膿菌(MDRP)について
Q21.多剤耐性アシネトバー(MDRA)について
Q22.耐性菌対策として、患者に伝播することを防ぐための感染対策は何か
Q23.耐性菌対策として、薬剤耐性菌を出現させない努力は何か
Q24.ASTとは何か
Q25.ワンヘルスアプローチとはどのような考え方か
Q26.ワンヘルスアプローチではどのように取り組んでいくのが良いか
通常の有効薬剤濃度では発育が阻止されない菌
薬剤感受性菌
病原体を化学物質のはたらきで殺し、またはその発育を阻止して、宿主の持つ防御機構と協力しあって感染症を治癒させる治療法。
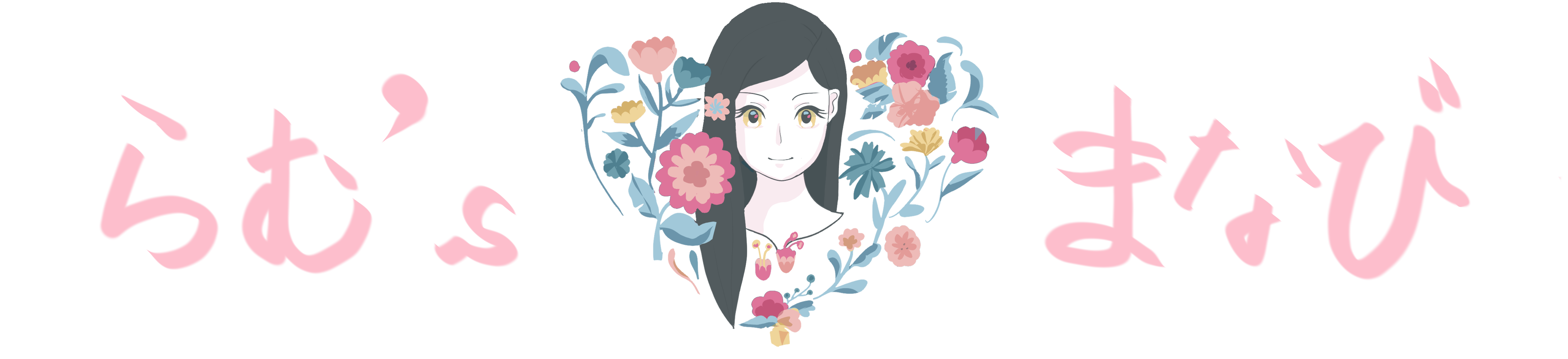


コメント